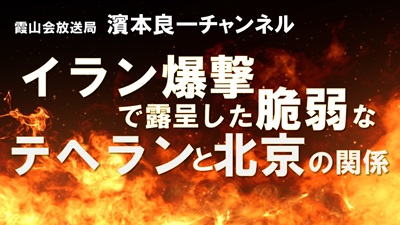第3回 ヨーロッパ留学に至るまで 嵯峨隆

ヨーロッパ留学に至るまで
近衞篤麿は19歳から、独学で和漢洋の様々な学問を渉猟し知識を広めた。そしてこの頃から、それまでに書かれた手記に加え、折に触れての見聞や感想を、『螢雪余聞』として書き溜めていった。ここに書かれた文章からは、青年時代における近衞の旺盛な知識欲と、倦むことのない向上心を窺うことができる。
『螢雪余聞』に書かれた文章を読むと、当時の近衞の関心は多岐にわたっていたことが分かる。中でも、すでに人種問題に関する文章を著していたことは興味を惹く。執筆時期は不明であるが、それは「日本人種論」と題したもので、横山由清の「日本人種論並良賤ノ別」(1879年)の読後感を記したものである。
横山によれば、古来東アジアの地では人々の往来が容易であったため、移住者の中で優れた者は、その土地の君主・将相・牧宰・吏卒となって、民衆を統治し教育を施し、風俗を改良したとされる。そして日本においては、東北・蝦夷の民も「終には華夷混同して同一種の人となれりしなるべし」と述べていたのである。こうした横山の記述を、近衞は「信をおくに足らんか」と肯定的に評価している。彼は横山の唱える東アジア民族の歴史的混合説を認め、同一人種説の立場を示していたのである。近衞が東アジアを一体とする見方の起源は、ここにあったといえるであろう。
近衞が最も力を注いだのは英語の学習であった。学習成果は目に見えて上がったのであろう、彼は次第に海外留学を望むようになった。当初、彼が希望する留学先はイギリスかアメリカであったため、その旨を三条実美(太政大臣)、岩倉具視(右大臣)、徳大寺実則(宮内卿)らに告げ、斡旋してくれるよう願い出た。
これに対して、三条と徳大寺は時期尚早という理由から、また岩倉は自由主義の影響を受けることを嫌ってこれに反対した。岩倉によれば、英米両国のごときは自由民権思想が極めて盛んで、こうした思想は日本の国体や国風と相容れるものではない。もし近衞が彼の地に留学したならば、知らず識らずのうちに感染し、これを信奉することとなるだろう。そして帰国後、この思想を社会に宣伝したならば、日本固有の名教を破壊し、ひいては不測の危害を生じさせかねないとされたのである。
岩倉は、近衞がどうしても海外に出たいというのなら、君主独裁制を採るロシアにすべきだと勧めた。しかし、ロシア語学習経験のない近衞が、これに応じるはずはなかった。どうにかして英米留学を実現させたい近衞は、旧師や友人に相談して回った。そして、駐露特命全権公使の任を終えて帰国した柳原前光(さきみつ)は、近衞の留学希望の熱意を知るに及んで斡旋の労を執ることとなった。柳原家は近衞家の支流であったため、前光は篤麿の希望を実現させるべく動いたのである。
柳原が斡旋に動こうとした時、近衞の英米留学に頑強に反対していた岩倉は世を去っていた(1883(明治16)年7月没)。すると、三条と徳大寺はこの問題に口出しすることはなくなった。そして、徳大寺に代わって宮内卿となった伊藤博文は近衞の希望に応じるべく奏請し、遂に1884年9月27日にオーストリア留学が認可された。留学先がなぜ英米ではなくてオーストリアだったのかといえば、日本の国体と国情を鑑みて、皇帝権限の強い同国が最適だとされたためであった。なお、近衞は同年7月に公爵に列せられており、翌年3月には前田衍子(さわこ)(加賀藩主・前田慶寧の娘)と結婚している。
近衞がオーストリアに向けて東京を出発したのは、1885(明治18)年4月18日のことであった。翌日、彼はフランス船ボルガ号にて横浜を出航した。それからの航程は日誌「航西紀行」(『螢雪余聞』所収)に記されているが、出航の日に当っては「余元より積年の宿志を達せしことなれば、心は壮快に覚ふれども、故国を去るの悲嘆は是れ人情の免れざる所なれば、家を出しとき、老厳公(祖父忠恢を指す-筆者註)に分袂せしとき、及び船中にて諸子に分れしときは、実に心細く覚へたりし」と率直な心境を綴っている。
近衞は航海の途中、アジアの現状を実見していくことになる。4月24日、澎湖島に立ち寄った際、彼は清仏戦争後の当地の状況を見て、次のように記している。「已に仏国旗の所々に翻へるを見る。已に碧眼の占むる所となりしや知る可(べ)し。愍(あわ)れむべき哉。然れども我国も隣国の地漸次に西人の蚕食する所となる、何ぞ之を対岸の火視して抛却して可ならんや。唇亡歯寒の喩鑑みるべき也」。ここには、未だ情緒の域を出ないものの、西洋対アジアという考えが生じていたことを窺うことができる。
しかし、2日後に上陸した香港では、中国人の生活の不衛生さに辟易する思いを綴る。曰く、「路傍土人を見るに辮髪にして跣足(はだし)也。土人の市街は臭気に堪へず。輿丁車夫[中略]衣服日本に未だ見ざる所ろの汚穢也」。近衞としては、これがかつての栄華を誇った中国社会の現実なのだという思いがしたであろう。他方、シンガポールにおいて金銭をせびる子供たちに、船上から小銭を投じて「船中の善き慰み」とする姿勢からは、日本のエリートという高みからするアジアへの眼差しが感じられる。
6月7日、近衞は目的地であるウィーンに到着した。翌日の日誌には、「是より勉学に従事し、又五年淹留中の行記を筆するの暇あらざれば、今日を以て限りとし、是に於て筆を擱す」と記されている。ここからは、学問に対する並々ならぬ決意を窺うことができる。そのことは、到着後彼が詠んだとされる、次の一首にも表れている。
波あらき千里の海も過にけり いざ分けいらむ文のはやしに
苦労を重ね、ようやくここまで来たという思いが伝わってくる。かくして、22歳の近衞篤麿はオーストリアで、そしてその後はドイツで学問の研鑽に励み、大きな成長を遂げることになるのである。
《近衛篤麿評伝》前回
《近衛篤麿評伝》次回
《近衛篤麿評伝》の記事一覧へ