第1回 近衞篤麿 忙中閑あり 嵯峨隆
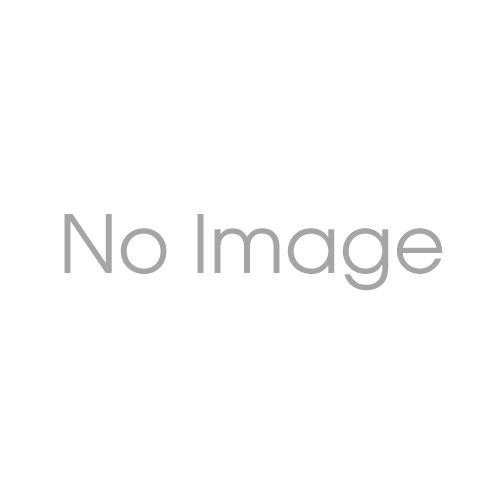
近衞篤麿と落語
近衞篤麿の生涯については、昨年上梓した『東亜同文会初代会長 近衞篤麿』(霞山アカデミー新書)において、やや詳しく論じておいたところである。紙幅の都合もあって、同書では近衞の私人としての側面にはほとんど触れなかった。そこで、以下においては、近衞の趣味や日常生活のエピソードを取り上げて紹介していくことにしたい。
公家しかも五摂家筆頭の当主である近衞篤麿と、庶民の娯楽である落語との取り合わせは一見して不釣り合いである。だが、日記などを読むと、彼がかなりの落語好きだったのではないかと推察される。
近衞の文章の中で、初めて「落語」という文字が出てくるのは、ドイツ留学中の1886(明治19)年、23歳の時のことである。それは「落語二件」と題された短編の文章で、後に編まれた『螢雪餘聞』の中に収められている。そこでは次のように記されている(原文は片仮名、句読点なし)。
「落語は元より一夜の笑柄(しょうへい)[=笑いの種]とするに過ぎざれども、中には其趣向の面白くして理屈に積しものもありて、随分我々法学生に故(ことさ)らに面白く感ずるものなきに非ず。余少にして落語を好み、其嘗て聴き得しもの及(およば)んと其数を知らず。今其中の巧みなるもの心頭に浮み来らず。後日の備忘の為めに録せんとす」。
以上のように書いた後、近衞は落語二席の粗筋を記している。そのうちの一席は演目が思い浮かばないのだが、もう一席は「始末の極意」の中の「鰻の嗅ぎ賃」だということがわかる。ストーリーは次のようなものだ。あるけちな男が鰻屋の隣に住んでいて、食事時になると、いつも店から流れてくる蒲焼の匂いをおかずにして飯を食べていた。これを知った鰻屋の店主が、月末に「匂いの嗅ぎ代」を請求に来たところ、この男は財布を出したものの、金を渡さずに店主の目の前で落として銭の音を鳴らし、「『嗅ぎ代』だから音だけでよかろう、銭を受け取ったつもりで帰れ」と言って追い返してしまった。
この文章を書いたころ、近衞は法律を学ぶ決意を固めていたのだが、この噺のいかなる部分が、法学生にとって「故らに面白く感ずるもの」だったのかと考えてしまう。推測だが、彼が一時商法を専攻しようと考えていたことからすれば、或いはこの噺の中の法律の想定しない商取引に感心したのかもしれない。それにしても、ドイツへ渡って一年余りで、語学の習得をはじめとして、学業に多忙な時期であったにもかかわらず、落語についての関心を持ち続けていたのだから、近衞にはかなりの精神的余裕があったということができるだろう。
それでは、近衞はいつごろから何処で落語を聴いていたのだろうか。上に引用した文章には、「少にして落語を好み、其嘗て聴き得しもの及んと其数を知らず」とあるので、京都在住時から聴いていた可能性はある。しかし、本格的に聴くようになったのは1877(明治10)年7月に14歳で上京した後のことだろう。
今と違ってマスメディアが発達していない時代のことであるから、当時は寄席に行って聴く以外に方法はなかっただろう。1884年発行の『東京案内』(錦栄堂)によれば、「東京府下の有名寄席」は87軒を数えている。それらを調べてみると、近衞が住んでいた麹町区にも数軒あり、元園亭という寄席は下二番町の自宅から徒歩圏にあったことがわかる。記録には残されていないが、大学予備門を中退した後、近衞は家居独学の合間に寄席に通っていたのではないだろうか。それも、かなりの回数に上っていたものと推測される。
近衞は1890(明治23)年6月にライプツィヒ大学を卒業後、9月に帰国して貴族院議員となった。その後、彼は寄席に通ったのだろうか。もちろん、行こうと思えば行くことはできただろう。しかし、現在残されている日記(1895年2月~1903年3月)には、寄席に触れた記述はまったくない。むしろ、近衞が落語を聴くのは宴会の余興が主だったようだ。場所は大体、湖月楼や紅葉館といった東京を代表する高級料亭であった。
近衞の日記には、宴会で落語を聴いたという記述がしばしば見られる。例えば、1897(明治30)年1月5日には「四時過一条(実輝)公と同乗して紅葉館に於ける緩話会に出頭、円喬の落語、館妓の踊等ありて盛会なり」とあり、また99年3月10日には「緩話会よりの(外遊の)送別会に臨む。甚だ盛会なり。円遊の落語、同人及び右円遊の茶番あり」などとある。宴会には落語家のほかにも、講談師の桃川如燕や早川貞水なども出演していた。当時から、宴席に芸人を呼ぶことは一般的だったのだろう。
近衞の日記では、演目や感想はまったく記されていないので、彼の好みなどについて知ることはできない。ただ、日記に最も多く名前が出る落語家が三遊亭円遊(初代)であったことには納得できるものがある。というのは、円遊は当時の東京の落語界では大人気を博していたからだ。噺も上手かったのだろうが、人気があった理由はまた別にある。それは「ステテコ踊り」というものだ。
落語史の本によれば、それは次の様なものだったという。噺を一席終えた後、円遊は立ち上がり、尻っぱしょりで半股引を見せて、「向こう横丁のお稲荷さんへ、一銭あげて、ざっと拝んでお仙の茶屋へ…」という下座の唄に合わせて、自慢の大きな鼻をちぎって投げる仕草をしながら、「ステテコ、ステテコ」と囃しながら踊るというものだった。いわゆる珍芸の走りなのだが、この奇抜さが当時の観客に大受けしたのだ。
果して、円遊は宴会でも演じていただろうか。近衞がこの踊りを見たとしたら、肥満の体を揺すってさぞや笑ったことだろう。公人としての謹厳さが伝えられているだけに、その様子を想像するだけで楽しいものがある。
《近衞篤麿 忙中閑あり》の記事一覧へ
ツイート




