第2回 近衞篤麿 忙中閑あり 嵯峨隆
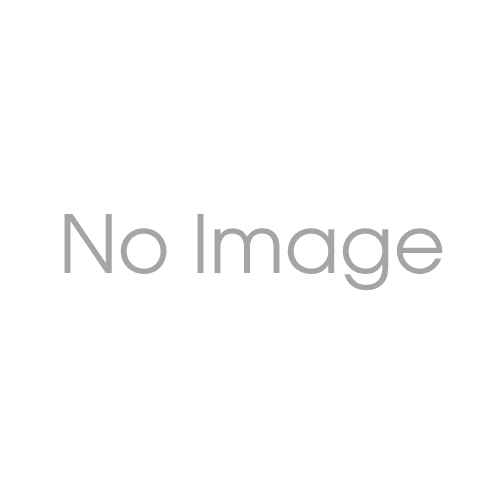
近衞篤麿の酒にまつわる話
近衞篤麿は若い頃から酒好きだったようだ。一回の酒量もかなりのものだったとみえる。1886(明治19)年6月、留学先のドイツから祖父・忠煕に宛てた書簡に、次のような一節がある。
小子(篤麿)も近頃は余程養生家に相成(あいなり)、当地名物のビールも一向不飲(のまざり)候。日本に居(おり)候頃ビールは五本、葡萄酒なれば二本、日本酒なれば一升も飲候事、今日よりは不思議に御座候。
この時、近衞は23歳。文章から推して、自分が他の人より飲める口だと自認していたことが窺える。彼が振り返る「日本に居候頃」というのは、自宅で独学生活を送る19歳からのことだろう。未だ行き先が全く見えない状況の中では、酒は息抜きをするに格好の道具だったのかもしれない。なお、付言しておけば、当時は10代で飲酒しても、これを禁じる法律はなく、取り立てて咎められることもなかったはずだ。
念願が叶って留学願いが認められ、近衞はオーストリアに渡った。そして彼はドイツに移り、ボン大学への入学を計画していた。上記書簡は、その頃に書かれたものだ。学問上の転機に当り、彼は好きなビールも控えて勉学に努めようとしたのであろう。
だが、決意は続かなかった。近衞はこの年の9月に祖父に宛てた書簡において、暑中休暇中の無聊の中で、「別に致し方も無之(これなく)、昨今は読書も不致(いたさず)ふらふらと酒飲暮し居候」と書いているのである。しかし、彼は決して禁酒が続かなかった自分の不甲斐なさを嘆いていたわけではなかった。続く文章では次のように記している。
独逸(ドイツ)人の大酒は申上、御承知の事に候が、其中に入りても昨今では余りひけを取らぬ位に相成候。兎角此事が御心配をかける種に御座候。
近衞は、自身がドイツ人ほどの酒飲みになったと認めているのである。ここには、悪びれた様子は全く窺えない。彼がこのように書くのには理由があった。それは、ドイツ人学生との「ビールの決闘」に勝ったことであった。大仰に「決闘」とはいうが、早い話が酒飲み競争である。
後年、近衞が語ったところでは、ある日、ドイツ人学生から決闘を申し込まれた。「決闘を申込まれて之を避けるといふやうな卑怯な振舞もならず、迷惑ではあるが直に快諾を与へた」という。当人は「迷惑」と述べているが、ドイツ人から大酒飲みと認定されたのだから、内心は満更でもなかったのではないだろうか。
決闘は厳正に選ばれた「介添人」の指示に従って行われた。まず、決闘者はテーブルを挟んで対座し、二人の前には大きなジョッキが置かれ、それになみなみとビールが注がれた。そして、号令のもとに一気に飲み干す。すると、すぐに注ぎ込んでまた飲む。これを繰り返す中で、最終的に飲めなくなった方が負けとなるというもので、極めて単純な競争であった(なお、トイレに行きたくなった場合についての説明もあるが、ここでは敢えて省略する)。
この時、近衞は20数杯を立て続けに飲んで「立派に勝った」という。ところが、相手方の介添人からクレームが付けられた。近衞が一滴こぼしたというのだ。言い掛かりを付けられた以上は絶対に勝たねばならぬ、日本の名誉のため死んでもかまわぬとの思いから、再戦の申し出を受けて立つことにした。相手は近衞の気迫に圧されたのか、今度は数杯飲んだところであっけなく勝負がついた。すると、列席の友人たちは拍手して、「近衞君万歳!」「日本万歳!」と叫んだ。近衞はといえば、酔いが回って前後不覚となり、這々の体で下宿に戻ったということである。
学問に精を出す一方で、近衞は異郷での青春生活を楽しんでいたのだ。祖父への書簡の背後にある気持ちの一端が分かるような気がする。しかし、たかだか酒飲み競争に「日本の名誉」のためには死んでも良いとしたことなどは、まさに若気の至りというべきだろうか。今日からすれば、ただ苦笑するほかはない。
大学を卒業後、日本に戻り政治家となってからの近衞は、さすがに学生時代のような飲み方はできなくなった。料亭の宴席で、芸妓の舞を見ながら飲んでいるかのような、いかにも当時の政治家らしい歓楽の有様を想像してしまう。
しかし、ドイツで飲んだビールの味は忘れられなかったようだ。日記には、時々「ビール会」に出席したという記述が見られる。1899(明治32)年4月から、近衞は海外視察の旅に出るが、何回か開かれた送別会のうちの一つは、帝国ホテルにおける独逸ビール会によるものだった。帰国後、近衞は各種の集会で視察報告を行っているが、同年12月22日、ドイツ留学経験者の集まりと思しき独逸会の会合では、ヨーロッパ事情についてはさておくとして、「唯特に報告すべき事こそあれ。そは他事にあらず。『独逸麦酒は旧によりて甘(うま)し』との一事是れなり」と述べた。これはまさに、近衞の「ビール愛」を表す言葉だといえるだろう。
政治家ともなれば、様々な宴席に招かれるものと見える。しかし、中には散々な事態になったこともあった。1900(明治33)年3月7日から茨城県を訪れた時のことだった。本来、公務でやって来たのだが、知事不在とあって予定は取りやめとなり、8日は弘道館をはじめ各地を観光して回った。そして、大洗に到着して魚来庵別荘という旅館に投じた。近衞は風光明媚にして閑静な環境に満足したようだ。
夜に入ると、同行の新庄直陳(なおおぶ)(旧麻生藩主の流れを汲む人。貴族院議員)は宴席の座興として、磯浜から芸妓数名を呼び寄せた。近衞は当日の日記に、これを「蛇足なりし」と記した。というのは、この芸妓がとんでもない女性たちであったからだ。続く文章には次のようにある。
土臭を帯びたる怪物は忽ち顕れ出たり。而して大に酒間の興を助けんとして、大妓二人迄は自ら酔倒せり。又雑風景の至りなりしも、又嘔吐の声楼下に聞こえて夜半近く迄止まず、漸くにして辞し去りしは憫然なりし。
大妓というから、年嵩のいった女性だったのだろうか。その怪物と称される芸妓が、客をもてなしているうちに、自分たちも飲んでしまい、遂に酔いつぶれてしまったというのだ。その場景を見て、近衞はおそらく苦々しく思ったことだろう。しかし、この文章からは怒りの気持ちは窺えない。むしろ、心なしかユーモアのようなものさえ感じてしまう。それは、長年培った酒飲みの度量の現れとでも言うべきものであろうか。
《近衞篤麿 忙中閑あり》前回《近衞篤麿 忙中閑あり》次回
《近衞篤麿 忙中閑あり》の記事一覧へ
ツイート





