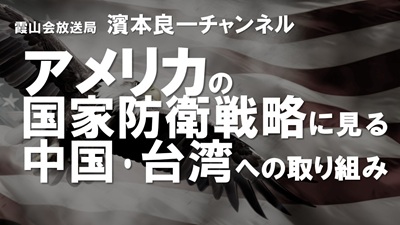第5回 近衞篤麿 忙中閑あり 嵯峨隆

やはり相撲が好き
近衞篤麿が子供のころから相撲に熱中していたことは、前回述べたところだ。伝記によれば、近衞は京都の小学校に入学以来、友人と相撲を取っては喜んでいた。当時は京都でも相撲興行が行われていた。今日の我々からすれば、相撲といえば東京に本部を置く日本相撲協会主催の興行を考えがちだが、幕末・明治初期までは大坂・京都・江戸の三都で興行されていた。東京に移る14歳までの間に、近衞は京都相撲の情報に接することは多かったものと考えられる。
欧州から帰国して貴族院議員となってからは、相撲見物に頻繁に行くようになった。『近衞篤麿日記』には相撲に関する記述がしばしば登場する。最初に現れるのは1897(明治30)年1月5日の条で、そこには次のように記されている。
午後回向院角力見物す。一条実輝、対馬嘉三郎等棧棚(ママ)に来る。荒岩の小錦に勝ちしは大手柄と云ふべく、不知火の鳳凰に勝ちしも又妙、その他面白きもの数番ありたり。
回向院は現在の墨田区両国にある寺院で、1768(明和5)年以降、境内で勧進相撲が興行されていた。当時は年二場所制で、1月と5月にそれぞれ10日間行われていた(晴天日のみ)。この日は興行の初日であり、近衞は知人の一条(貴族院議員)と対馬(実業家)を誘っての見物であったようだ。
上記文中にある荒岩(名は亀之助)は、入門からわずか3年で出世階段を駆け上がり、新入幕を果たしたばかりの新鋭力士であった。これが、当時の横綱(第17代)である小錦(初代)を破ったのだから、近衞が「大手柄」と評したことには十分頷ける。この場所、荒岩は7勝1敗1分1休という好成績を収めている。当時はまだ優勝制度はなかったが、それに相当する成績であった。
近衞は10日にも回向院に出かけている。しかしこの後、日記には荒岩の活躍をはじめ、この場所の相撲についての記述は見えない。それは翌11日の英照皇太后の崩御によるものであった。天皇家に最も近い五摂家筆頭の家系であり、しかも貴族院議長の立場でもあったため、喪に服すことは当然のことであり、当分の間は相撲の話も控えざるを得なかったのであろう。
近衞が次に相撲見物に出かけたのは1年後のことであった。1898(明治31)年1月13日の日記には以下のようにある。
回向院相撲見物に赴く。満一ヶ年これをみず。其間大変動はなかりしも、小錦の鋭気は衰へたるものか、もしくは他の上達したるによるか、何れにしても前日の観なし。逆鉾、荒岩の敏捷なる、鳳凰、朝汐の勇猛なる、源氏山の老練なる、皆前年に異ならず。唯梅ケ谷、常陸山の上達驚くべく、本場所に大人気は主として此二人の力によるといふべし。
小錦の全盛期はすでに過ぎていた。代わって、梅ケ谷と常陸山の力は急上昇していた。彼らに対する近衞の期待が高かったことは前回に述べたところだ。この場所、近衞は3日間回向院に通ったが、千秋楽は雨天の中での観戦であったと記されている。なお、この場所の優勝相当力士は、「勇猛なる」と評した大関の鳳凰であった。
近衞は本場所の取組だけではなく、相撲部屋の稽古の見物にまで出かけていた。1899(明治32)年2月12日のことだが、板垣退助と連れ立って両国の伊勢ノ海部屋を訪れている。そこで目にとまった1人の力士がいた。「越中産の大男、年は二十二にして身長六尺二寸、体重二十四貫の者」とあるから、約188センチ、90キロといった体格だ。
名も知れぬ男だが、この日初めて相撲を取ったのだという。稽古の様子を見た近衞は、「三枚目力士位は倒すになにの苦もなきが如し。将来多望なりといふべし」と記している。前回の文章で、近衞の力士評価は優れていると書いたが、この力士は果たして後に大成したのだろうか、気になるところだ。
稽古を見た後は、板垣らとともに料理屋・坊主軍鶏で昼食を取った。座には鳳凰、玉の井といった力士数名も同席している。近衞は力士たちに飲み食いさせるのが好きだったようだから、一流のタニマチであったと言えよう。ちなみに、この店は軍鶏料理で有名で、落語の「船徳」にも出て来るので知っている人も多いと思う。今は「ぼうず志ゃも」という店名だが、池波正太郎の「鬼平犯科帳」に出て来る料理屋「五鉄」のモデルになったとも言われている(ただし異説もある)。
話を相撲に戻そう。1900(明治33)年以降になると、近衞の回向院通いも正月場所・夏場所とより頻繁になり、日記における講評も熱がこもったものとなる。同年1月13日の日記を見てみよう。
回向院相撲見物(初日なり)。世評高かりし源氏山、国見山の取組は、種々世評ありしにも関らず、国見はあまりにあせり、立上るや源氏得意の左差しとなりしかば、忽ちにして下手投げ極りて、源氏の勝は老練の取口といふべし。
この後の数日間の日記にも詳しい講評が綴られている。おそらく取り組みごとにメモを取っていたのだろうが、近衞の書きぶりはもはや素人の域を脱しているかのようである。しかも、この間の近衞は貴族院議長として、学習院院長として、そして東亜同文会の指導者として極めて多忙な生活を送っていたので、どのようにして相撲見物の時間を作り出していたのか不思議に思えるほどである。とにかく、近衞が世間一般の相撲好きとは次元が違っていたことは確かなようだ。
さて、近衞は相撲のあり方について独特の考えを持っていた。当時、相撲を論じる者の中には、力士には時代にふさわしい教養を施す必要があるとする声もあった。これに対して、「力士は無学文盲にて無鉄砲」であることが良いとして、「教育抔あるは却て縮退を来す種にて、只々其無邪気なるが愛すべき焦点なり」と述べている。極端な意見に聞こえるが、近衞としては知識や教養よりも、精神的に伸びやかな力士を理想としたのである。
むしろ、近衞は当時の社会的環境が相撲の発展の障害になっていると考えていた。それは、力士を含めて勝負による栄辱にこだわらない風潮、相撲を遊芸見世物と見なす傾向、そして徴兵制の問題である。最後の徴兵制が力士たちの相撲生活にどの程度の影響を与えたのかは不明だが、近衞としては、西洋化の時代にあっても相撲は単なる見世物ではない、真剣勝負の格闘技であることを望んだのではないだろうか。
《近衞篤麿 忙中閑あり》前回
《近衞篤麿 忙中閑あり》次回
《近衞篤麿 忙中閑あり》の記事一覧へ
ツイート