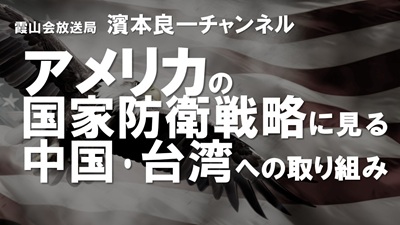第7回「中村進午」―対露強硬七博士の一人― 栗田尚弥

「中村進午」―対露強硬七博士の一人―
義和団事件に端を発する、清国と英米露日等列強8か国からなる連合軍との戦争(北清事変、1900―1901)は、連合軍の勝利のうちに終わった。戦後、列強は、1901(明治34)年9月に結ばれた辛丑条約(北京議定書)に基づき、北京と天津における駐留権を得たが、戦時中の占領地からは順次撤退していった。しかし、ロシア帝国のみは、条約締結後も戦時中に占領した「満洲」一帯の占領・駐兵を継続した。
これに対し、他の列強は厳重に抗議し、清国政府も不満を表明した。結局、1902年4月、清露間において満洲還付条約が締結され(於、北京)、ロシアは1903年10月までに3度に渡って撤兵を実施し、「満洲」の主権を清国に返還、同地を占領以前の状態に復元することに同意した。
しかし、第2次以降の撤兵は実施されず、1902年10月に実施された第1次撤兵も、撤兵とは名ばかりで、正規軍を鉄道守備隊(ロシアが管理していた東清鉄道の守備隊)に〈変身〉させただけであった。
このような事態に対し、日・英・米の3国は強く抗議し、日本国内では対露強硬論が沸き起こった。その象徴と言うべきものが、明治36(1903)年6月11日に『朝日新聞』紙上(全文発表は24日)に発表された「七博士意見書」である。
「七博士意見書」は、東京帝国大学教授の戸水寛人、同富井政章、同小野塚喜平治ら7人の博士が名を連ねた意見書で、対露武力強行路線にもとづきロシアの「満洲」からの完全撤退を求めていた。
博士7名のうち6名は戸水をはじめ東京帝国大学の教授であり、残りの1名が学習院の教授であった。このただひとりの学習院教授こそ、近衞篤麿がその将来を期待した中村進午博士であった。
中村進午(1870―1939)は、明治3年7月、旧高田藩士中村九郎の3男として、越後国高田(のちに新潟県高田市、現、上越市)に生まれた。明治24年、第一高等中学校(後の第一高等学校、現、東京大学教養学部)を卒業した中村は、東京帝国大学法科大学に進み、27年首席で卒業した。その後大学院に残り研究を続け、そのかたわら29年から30年にかけて、高等商業学校(のちに東京高等商業学校を経て東京商科大学、現、一橋大学)法律科の講師を務めている。
当初、中村は、国法学を研究していたが、国際法学者であった実兄前田盛江が夭逝すると、兄の志を継ぐためであろうか、専門を国際法に転じた。
明治30年1月6日、中村は学習院の教授に就任する。この時の院長が、近衞篤麿である(28年院長就任)。近衞の中村に対する期待は大きなものがあったようで、後に(明治33年)、京都帝国大学が、中村を招聘しようとした際には(要するに学習院からの引き抜き)、「学習院は文部に属せざれ共文部より教師を誘拐するが如きは断じて承知出来ず」(『近衞篤麿日記』第3巻)と憤慨している。また、35年には、一教授である中村の結婚式に近衞自らが出席している。
実は、中村の学習院教授就任は、前年にすでに決まっており、しかも教授就任後直ちに欧州に留学することが決まっていた。中村の教授就任、留学について近衞が尽力したことは想像に難くない。
明治30年1月23日、学習院教授就任後のわずか2週間後に、中村はドイツ・ライプチヒに向けて出発した。出発に先立ち、近衞は、ドイツ留学中の実弟津軽英麿に贈る書籍を、中村に托している。これが縁であろうか、ドイツ到着後、中村は津軽と親交を深めることになる。
30年4月、ドイツに到着した中村は、以後3年間(明治33年3月帰国)ドイツ(ライプチヒ大学)のみらず、英国のロンドンやフランスのパリにも赴き、学問(国際法)に磨きをかけている。その傍ら、欧州の国際関係や学問についての詳細な報告を、しばしば近衞に書き送っている。のみならず、自身の論文も近衞に送っており、明治31年3月には、ドイツの膠州湾租借について記した論文(ドイツ語)を送っている。これは、日清戦争後の三国干渉によって、日本の清国からの遼東半島租借を阻止したドイツが、清国から膠州湾を租借するのは論理的矛盾である、とするもので、ドイツ人の教授からは強く批判された(中村は自説を撤回せず)。また、明治32年4月から11月にかけて、近衞が「海外漫遊」の旅に出た際には、ボンにおいて近衞と落ち合い、近衞のドイツ滞在中行動を共にしている。
明治31年1月、近衞は「同人種同盟、附支那問題研究の必要」を、雑誌『太陽』に発表した。この論文は、内外の注目を集め、特にドイツでは、いくつかの新聞が近衞を「白人排斥論者」であると批判し、近衞発言が国際問題となることを懸念した駐フランス公使栗野慎一郎は、独紙「フランクフルト・ツァイツング」において近衞批判を展開した。
近衞の実弟津軽英麿も、白人優位の世界は、「優勝劣敗」の法則に照らしてもはや「已む得ざる」ものであり、日本はこの現実を直視し、中国を助けるよりも、白人列強の「仲間入り」すべきである、と兄の「同人種同盟」論を批判した(津軽英麿「近衞宛書簡」明治31年3月1日、『近衞日記』第2巻)。
中村もまた、近衞に自重を説いている。だが、それは津軽とは論調を異にする。中村も近衞同様、日清戦争後の日本(日本人)の驕慢化を憂え、このまま「(中国に対する)侮蔑審」がつのれば、やがては日本の「亡国」を招くと語り、中国を「友邦」とすることには賛意を表する(従って「支那保全」には賛成)。だが同時に、中村は、中国やアジア諸国の現状から判断して、これらの国々との「同盟」は不可能であり、かえって「同盟」は「欧米諸強国を敵」とすることになり「日本の不利益」を招く(中村「近衞宛書簡」明治31年4月12日、『近衞日記』第2巻)として、近衞に自重を求めたのである。当時、欧州ではすでに日本と英国の同盟がうわさされており、中村も日英の同盟を期待していたものと思われる。中村は、近衞の「同人種同盟」論が、日英間を「離間せん」(同上、同書)とする企みに利用されることを懸念したのではないだろうか。
明治33年3月、中村は帰国し、改めて学習院で教鞭をとることになった。学習院では、大学部の設置など、近衞の進める同校改革に積極的に参加している。一方、古巣の高等商業学校(35年、東京高等商業学校に改称)でも講師を嘱託され、35年からは兼任教授に任じられている。また、戸水寛人ら後の「七博士意見書」のメンバーとしばしば会同している。また、戸水が、松浦厚伯爵らと対外問題を議論するための団体、宣揚会を組織するとこれに参加している。中村の考え方は、他の6博士のそれとは必ずしも同じものとは思われないが(特に戸水とは)、「支那保全」、対外(ロシア)硬という点では、意見の一致を見ていた。
明治33年9月12日、近衞は、中村、戸水、富井らと「集合」を持ち、「種々運動の方法等」について「付打合は」せている(『近衞日記』第3巻)。近衞が、「支那保全」の立場から対外(ロシア)硬団体である国民同盟会を立ち上げるのは、この約2週間後(9月24日)のことである。以後、近衞は、中村、戸水らと屡々会合を持ち、34年の1月には、中村、戸水らに、「満洲問題に付学者としての尽力を促がし」ている(『近衞日記』第4巻)。
明治35年4月、国民同盟会は、露清間で満洲還付条約が締結されたため、「支那保全」の目的が達せられたとして解散した。しかし、ロシアは、還付条約で約束された第2次撤兵の期限(1903年4月8日)が近づいてもこれを実施しようとしなかった(第1次撤兵も先述した如く形式的撤兵)。この事態を懸念した近衞やその周辺では、国民同盟会の活動を再開すべく、対外硬同志会を結成、撤兵予定日の4月8日に上野公園梅川楼で大会を開いた。中村が、戸水らとともに「七博士意見書」を明らかにしたのはこの2か月後のことである。
「七博士意見書」は、一般世論からは概ね好意を持って迎えられた。対外硬同志会も活動を活発化させ、8月には近衞の意向を汲んで、改めて対露同志会(第2の国民同盟会と言われる)を結成した(近衞はすでに病床にあり、神鞭知常が委員長として会長代行)。しかし、体制側の「意見書」に対する評価は必ずしも芳しいものではなかった。たとえば、元老伊藤博文は、「意見書」に対し、「我々は諸先生の卓見ではなく、大砲の数と相談しているのだ」、と極めて冷淡だったという(ウィキペディア「博士意見書」)。
明治38年9月、中村は、学習院の教授と東京高等商業学校の兼任教授を辞任する。「(日露)媾話條条約反対上奏の責を負つ」た為だと言われている(「名誉教授中村進午博士逝く」『一橋論叢』第四巻第六号)。学習院および東京高等商業学校教授辞任後、中村は一時千葉県一の宮に閑居したが、翌39年、専任の教授として東京高等商業学校に復職、大正9(1920)年、同校の大学昇格と同時に、東京商科大学教授となり、昭和5(1930)年10月まで務め退官、名誉教授となった(退官後も非常勤講師として昭和13年まで講義を担当)。その他、早稲田大学、慶応義塾大学、中央大学、海軍大学校等の教壇にも立ち、拓殖大学の学監も務めた。昭和14年の中村の死後、その研究を支えた和漢洋の書物は、一橋大学、早稲田大学、拓殖大学に寄贈された。
《霞山人国記 栗田尚弥》前回
《霞山人国記 栗田尚弥》次回
《霞山人国記 栗田尚弥》の記事一覧