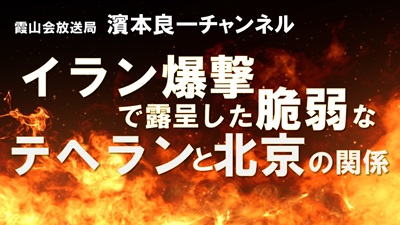第9回 ミャンマー報道の「同志」 伊藤努
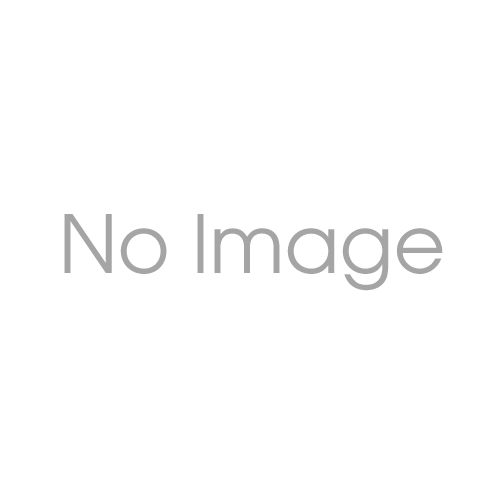
第9回 ミャンマー報道の「同志」
これまで世界のいろいろな国で取材してきたが、思い出も多く、記憶が鮮明なのは苦労した仕事だった時だ。実際の人生にも通じる経験則で、読者の皆さんも同意してくれるのであるまいか。そうした基準に照らして、いまだに忘れられないのがしばしば出張で赴いたミャンマー(ビルマ)である。
ミャンマーはご存知の通り、今から20年近く前の同国初の自由選挙で民主化運動指導者アウン・サン・スー・チーさん率いる野党の国民民主連盟(NLD)が圧勝したが、よもやの敗北を喫した軍部が政権の居座りを決め込み、今日に至っている。軍が国家運営の全権を握る軍事政権の下で、民主化を求めるスー・チーさんら反体制勢力は厳しい弾圧を受け、国内は時計の針が止まったかのような陰鬱とした空気に包まれている。
しかし、そういう中にあっても、1990年代後半の一時期、当時首都だったヤンゴンにあるスー・チーさんの自宅前の大学通りでは、熱気あふれる週末の対話集会や若者らの民主化デモが繰り返し行われ、それを取材していて、自分の国の沈滞を打破したいとする市民の願いが伝わってきた。民主化要求の拡大を恐れた軍政当局はその後、一転してデモを厳しく取り締まり、逮捕者が相次いだ。ノーベル平和賞を受賞したスー・チーさんも自宅軟禁下に再び置かれた。デモを取材した知り合いの記者が治安要員の暴行を受け、大けがをした例もある。2年ほど前には、フリーの日本人ジャーナリストが僧侶らのデモを取材中に兵士の銃撃を受け、死亡した。

ミャンマー軍に対し、抗議のデモを行う学生
記者と外交官は取材し、取材される関係で、両者の間にはそれなりの緊張関係が必要なのはもちろんだ。そうした節度を持ってM氏と接してきたつもりだが、ミャンマーの民主化問題といった大きな取材対象を前にすると、互いの立場の違いを超えて「同志的関係」も出てくるのは自然の成り行きだろう。東京でバンコク時代の記者仲間の集まりに現役外交官のM氏がほぼ欠かさず参加するのは、同氏の側にも同じ気持ちがあるに違いない。スー・チーさんの自宅軟禁や身柄拘束が延々と続くなど、民主化の前途は依然として険しい。集まりではいつも、多くの国民が苦難を強いられているこの親日国家の行く末をめぐる議論となる。特派員でもない今も変わらぬ元取材先との関係に、われながら苦笑する。