第607回 「現下の世界情勢・七不思議」(下) 伊藤努
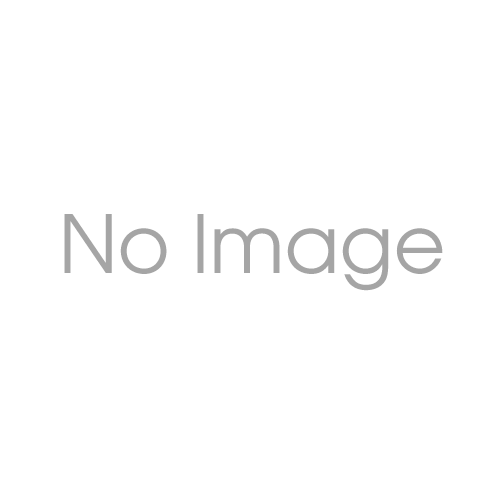
第607回 「現下の世界情勢・七不思議」(下)
前回に続き、国際情勢を日ごろウォッチしている筆者にとって大きな疑問の謎解きがなかなかできない「現下の世界情勢・七不思議」と題して、残る四つの理解が難しいテーマを紹介させていただく。前回の本欄では、驚きにも近いウクライナ戦争をめぐる不思議、欧米の厳しい対ロシア制裁の効果がなかなか上がらない謎めいた不思議、そして国際的に孤立し、慢性的な経済不振にあえぐ北朝鮮の独裁国家がなぜ巨額の資金がかかる核・ミサイル開発を長年にわたり継続できているのかという未解明の不思議を取り上げたが、四番手となるのは、世界の平和と安全に特別の責任を有すると国連憲章に明記された国連安保理の機能不全が長く放置されていることの不思議だ。
安保理では特に、第二次世界大戦の戦勝国である米国、英国、フランス、ロシア、中国の5カ国が常任理事国として特権とも言える拒否権を持ち、一国でも決議案に対して拒否権を行使すれば、決議は採択できない。今回のウクライナ戦争では、ロシアが国連憲章と国際法の重大な違反を犯したと国連総会決議で名指し批判されたにもかかわらず、常任理事国の地位を保持し、自らの拒否権行使によって法的拘束力のある安保理決議を葬り去り、侵略行為を糾弾されることもなかった。このようなことがまかり通るのがこれまでの安保理の仕組みであり、安保理が機能不全に陥るのも当然だ。
わが国を含め、ドイツ、インド、ブラジルの4カ国(G4)が主導する国連改革の取り組みでは、国際社会の多様な意見を反映できる常任理事国の拡大とともに、現行の拒否権行使のあり方の見直しについても議論されているが、そうした国連改革でさえ、ロシアや中国など一部常任理事国の反対がネックとなって、話が前に進まない状況が続く。80年近くも前の第二次大戦の戦勝5カ国だけに特権が付与された国連創設当時の時代状況と現在の国際社会の実態は様変わりだというのに、常任理事国が既得権を死守しようとするあまり、世界の平和と安全のために何ら実効性ある解決策を講じられないままの安保理が不思議な存在に映るのは驚き以外の何物でもない。
21世紀は、国際テロ組織「アルカイダ」が米旅客機を相次いで乗っ取り、ニューヨークの世界貿易センタービルに激突させるなどして決行した2001年9月11日の米同時テロによって激動の幕を開けた。犠牲者が3000人に上るという世界を震撼させた前代未聞のテロだった。これを機に当時の米国のブッシュ政権が対テロ戦争の開始を宣言し、アフガニスタン、イラクに相次いで軍事介入した。いずれも国連のお墨付きを得た上での軍事作戦ではなく、米国をはじめとする有志連合によるアルカイダなどのイスラム過激派掃討作戦と並行する形で急速に中東各地に広がったのが、イスラム教の二大宗派であるスンニ、シーア両派の武装勢力同士による武力抗争だ。
イスラム教徒が多数派を占める中東のアラブ諸国では、国家レベルでもスンニ派主導の政権とシーア派主導の政権による対立の構図は長く続いていたとはいえ、血で血を洗う両派の武装集団による抗争の激化はやはり、米同時テロを受けて米国がイラクに軍事介入し、当時のフセイン政権を打倒して以降のことだ。スンニ派、シーア派をそれぞれ後ろ盾とするイスラム過激派のテロ組織は中東やアフガニスタンから、政情不安が続く国家が多いアフリカに活動の場を移し、武力抗争を続けながら影響力の拡大を競い合っている。同じイスラム教徒がなぜ、そこまで憎悪を深めながら流血の争いを激化させるのか、異教徒の筆者にとって理解が難しい不思議の一つとなっている。
中国内陸部の大都市・武漢で2019年末、肺炎に似た症状の患者が相次いで死亡したことが、100年に一度とも言われる新型コロナウイルス感染拡大の始まりとなった。しかし、世界各国で700万人近い死者を出した新型コロナがどこから広がったかについては、パンデミックが一応終息した現在でも確認されていない。六番手の不思議がこの問題での中国の習近平指導部の不可解な対応だ。
これまでのところ、米エネルギー省や連邦捜査局(FBI)が言及した武漢ウイルス研究所からの流出説と、多くの専門家が唱えている動物からの飛び火説の二つの仮説がある。しかし、最初に武漢での感染拡大が報告された中国当局が流出源の特定や原因究明となると、情報公開どころか、隠ぺいするような姿勢を変えないのは大きな謎だ。
初期の感染拡大は、武漢の華南海鮮卸売市場から始まったことが分かっている。パンデミックさなかの2021年に武漢の海鮮市場で売られていたタヌキやアライグマなどの動物からヒトへの感染が広がったのではないかとする研究が米科学誌サイエンスに掲載された。これらの動物が売られていた屋台や動物が入っていたカゴから新型コロナウイルスが見つかっていることも、宿主とされるコウモリから感染した動物由来説を支持するものと考えられる。多くの人が国境を越えて移動するグローバル化の時代に、新型コロナのようなウイルス感染症のパンデミックは今後とも起こり得るが、新たな疫病の被害拡大を防ぐためにも、公衆衛生分野での国際的な協調の重要性は改めて指摘するまでもない。厳しい封じ込め策だった「ゼロコロナ政策」の終了で幕引きするのではなく、中国当局には今後の大きな教訓とするためにも流出源の特定と原因究明に取り組んでもらいたいものだ。
七不思議の最後に取り上げるのは、来年の米大統領選で返り咲きを目指すトランプ前大統領が共和党の候補指名レースで独走状態になっていることなど、数々の過激な発言やスキャンダルまみれの人物がいまだになぜこうも高い支持を得ているのかという疑問で、筆者にとっては不思議以外の何物でもない。
トランプ氏は前回大統領選の敗北を認めようとせず、熱狂的支持者に米議会襲撃を扇動するなど選挙結果を覆す工作や機密文書の不正所持での起訴を含め四つの事件で刑事被告人の身にあるが、本人は例によって「魔女狩りだ」「選挙妨害だ」などと自身の無実を訴えている。世間の常識では理解し難い身勝手な発言だが、国民の分断、党派対立が深まる米国の半数の有権者(共和党支持者)の多くには至極真っ当な常識も通用しないのが現実だ。それにとどまらず、起訴されるたびに支持率が上がるというのも理解を超える謎めいた現象だ。
自身を批判する人物や政敵、ライバルに対しては口汚い言葉で容赦ない攻撃を加え、それによってむしろ政治的に優位な立場に立とうとするトランプ氏の特異な手法について、ドイツの哲学者は「ベビー・モンスター」(赤子の怪物)と形容した。共和党指導部にも手を付けられない傍若無人の人物が再びホワイトハウス入りするようなことがあれば、不思議というよりも悪夢かもしれない。
《アジアの今昔・未来 伊藤努》前回
《アジアの今昔・未来 伊藤努》次回
《アジアの今昔・未来 伊藤努》の記事一覧




![“春天来了,花儿[ ]了。”](https://www.kazankai.org/dcms_media/image/caicaikan-archive.jpg)